株式会社サワダ製作所 代表取締役 澤田 浩一 の日記 | 経営者会報 (社長ブログ)
株式会社サワダ製作所 代表取締役 澤田 浩一 の日記です
前ページ
次ページ
2007年04月12日(木)更新
オンとオフ
<質問>
プライベートと仕事は完全に分けて考えていらっしゃいますか。それとも両者の区別はなく、「仕事が趣味です」と言い切れるほうでしょうか。
(東京大学教養学部3年 小川明浩さん)
時間上でも意識の上でもプライベートと仕事はあまり分けてはいません。
休んでいてもふとしたことで仕事のことを考えたりはします。
時々夢の中でも・・・・(笑)
さすがにそういう時は起きた時、身体全体が「しんどいなぁ」と思います。
そうでなければ、ふっと違う視点で仕事を考えたりすることもあるので、プライベートと仕事をあえて分けて考える必要もないんじゃないかと思っています。
要は自分の中の生活のリズムというか、流れみたいなのに沿っていれば良いのかな、と。
<質問>
精神的な「オフ」はありますか。もし、おありでしたら、どのようにして切り替えていらっしゃいますか。もし「オフ」がないとしたら、辛くはありませんか。
(東京大学3年 須田悠太さん)
意識してプライベートと仕事を分けてない分、精神的な「オフ」は自然と取っています。
最近のオフは漫画を読んでるか、DVDを観てるとき、あと会社からの行き帰りの車の中で音楽を聴いているとき。
時間は短いけど、気持ちが休まる貴重な時間です。
漫画は少年・少女問わず好きなので、寝る前の10分とか、ヒマを見つけては読んでは時々ウルウルしてますよ(笑)
「オフ」を取って自分から進んで余裕を持とうとする意識は大事だと思います。
トップの仕事は各部署を見渡して、必要な時に必要な指示を行うこと。
うまくいかないことも多いですが、自分に余裕がないとそういうことはできません。
プライベートと仕事は完全に分けて考えていらっしゃいますか。それとも両者の区別はなく、「仕事が趣味です」と言い切れるほうでしょうか。
(東京大学教養学部3年 小川明浩さん)
時間上でも意識の上でもプライベートと仕事はあまり分けてはいません。
休んでいてもふとしたことで仕事のことを考えたりはします。
時々夢の中でも・・・・(笑)
さすがにそういう時は起きた時、身体全体が「しんどいなぁ」と思います。
そうでなければ、ふっと違う視点で仕事を考えたりすることもあるので、プライベートと仕事をあえて分けて考える必要もないんじゃないかと思っています。
要は自分の中の生活のリズムというか、流れみたいなのに沿っていれば良いのかな、と。
<質問>
精神的な「オフ」はありますか。もし、おありでしたら、どのようにして切り替えていらっしゃいますか。もし「オフ」がないとしたら、辛くはありませんか。
(東京大学3年 須田悠太さん)
意識してプライベートと仕事を分けてない分、精神的な「オフ」は自然と取っています。
最近のオフは漫画を読んでるか、DVDを観てるとき、あと会社からの行き帰りの車の中で音楽を聴いているとき。
時間は短いけど、気持ちが休まる貴重な時間です。
漫画は少年・少女問わず好きなので、寝る前の10分とか、ヒマを見つけては読んでは時々ウルウルしてますよ(笑)
「オフ」を取って自分から進んで余裕を持とうとする意識は大事だと思います。
トップの仕事は各部署を見渡して、必要な時に必要な指示を行うこと。
うまくいかないことも多いですが、自分に余裕がないとそういうことはできません。
2007年04月09日(月)更新
枚岡合金工具様 経営計画発表会
経営者として尊敬する先輩であり、経営者会報ブログでもブログを書いておられる古芝社長の枚岡合金工具株式会社様において経営計画発表会が行われました。
弊社ではISO9001に沿って毎年短期の経営計画を立てていますが、このように内外から人を集めて発表する、というところまでは行っていません。
経営計画発表会を通して、社員さんが自ずから目標に対しコミットメントを行うことはモチベーションを高め、また計画が外部の方からの目にさらされることで切磋琢磨されていくのだと思います。
弊社でもいずれは取り組みたいことのひとつです。
経営計画では、PDCA(計画・実行・チェック・アクション)サイクルが重視されますが、このうちもっとも比重をかけなければならないのはP(計画)です。
明確な目標があることを前提として、
・何を行うのか、
・目標を達成するために、なぜそれをおこなわなければならないのか
・それを行うための手段・方法は何なのか、
・なぜその手段・方法なのか、
・その手段・方法を行うためにはどのような障害があるのか、
を明らかにし、社内で共有できれば最高だと思います。
実際はなかなかそううまくは行かないのですが、それらのことをテンプレートにまとめ実行に導くのが、ゴールドラット氏のバイアブル・ビジョンでしょう。
弊社ではISO9001に沿って毎年短期の経営計画を立てていますが、このように内外から人を集めて発表する、というところまでは行っていません。
経営計画発表会を通して、社員さんが自ずから目標に対しコミットメントを行うことはモチベーションを高め、また計画が外部の方からの目にさらされることで切磋琢磨されていくのだと思います。
弊社でもいずれは取り組みたいことのひとつです。
経営計画では、PDCA(計画・実行・チェック・アクション)サイクルが重視されますが、このうちもっとも比重をかけなければならないのはP(計画)です。
明確な目標があることを前提として、
・何を行うのか、
・目標を達成するために、なぜそれをおこなわなければならないのか
・それを行うための手段・方法は何なのか、
・なぜその手段・方法なのか、
・その手段・方法を行うためにはどのような障害があるのか、
を明らかにし、社内で共有できれば最高だと思います。
実際はなかなかそううまくは行かないのですが、それらのことをテンプレートにまとめ実行に導くのが、ゴールドラット氏のバイアブル・ビジョンでしょう。
2007年04月05日(木)更新
カリスマ性について
<質問>
経営者には、やはりカリスマ性が必要だと思われますか。もし必要ならば、それを培う方法はありますか。それとも、カリスマ性とはそもそも先天的なものなのでしょうか。
(東京大学教養学部3年 小川明浩さん)
今は亡き私の父は会社の創業者で、こうと決めたら梃子でも動かないほど頑固な人でした。
きっと会社でも社員さんを困らせていたんだろうなと思うのですが、社員さんからは結構良い想い出しか聞かないので、そういう意味ではたぶんカリスマ性のある経営者だったんだろうと思います。
私の場合はどうかと言うと、逆にカリスマ性などというものとは縁遠い性格です。
小さいころから怖がりのあがり症で、今でも人前で話をしたり、歌うことは苦手です。
ですが、
「社員はトップの言動をいつも注目している」、
言葉ではほんの一言なのですが、日々の社員さんのちょっとした動きや言葉でひしひしと身をもって感じることがあります。
日々の事業の営みの中でこのような実感を持ったり、またいろいろな判断や決断をしていると、トップとしてリーダーシップを発揮したり、また方針や方策を決めていくことへの責任や自覚が培われてきているように思います。
カリスマ性も経営者の持ち味のひとつだと思いますが、 肝心なのは今後会社をどうしていきたいか、の想いです。
こうありたい、という想いが、責任への自覚やリーダーシップ、あるいはカリスマ性、というものを培うのではないでしょうか。
経営者には、やはりカリスマ性が必要だと思われますか。もし必要ならば、それを培う方法はありますか。それとも、カリスマ性とはそもそも先天的なものなのでしょうか。
(東京大学教養学部3年 小川明浩さん)
今は亡き私の父は会社の創業者で、こうと決めたら梃子でも動かないほど頑固な人でした。
きっと会社でも社員さんを困らせていたんだろうなと思うのですが、社員さんからは結構良い想い出しか聞かないので、そういう意味ではたぶんカリスマ性のある経営者だったんだろうと思います。
私の場合はどうかと言うと、逆にカリスマ性などというものとは縁遠い性格です。
小さいころから怖がりのあがり症で、今でも人前で話をしたり、歌うことは苦手です。
ですが、
「社員はトップの言動をいつも注目している」、
言葉ではほんの一言なのですが、日々の社員さんのちょっとした動きや言葉でひしひしと身をもって感じることがあります。
日々の事業の営みの中でこのような実感を持ったり、またいろいろな判断や決断をしていると、トップとしてリーダーシップを発揮したり、また方針や方策を決めていくことへの責任や自覚が培われてきているように思います。
カリスマ性も経営者の持ち味のひとつだと思いますが、 肝心なのは今後会社をどうしていきたいか、の想いです。
こうありたい、という想いが、責任への自覚やリーダーシップ、あるいはカリスマ性、というものを培うのではないでしょうか。
2007年03月30日(金)更新
さまざまな工夫をこらして製品カタログを改訂しました
この度、製品カタログを改訂しました。
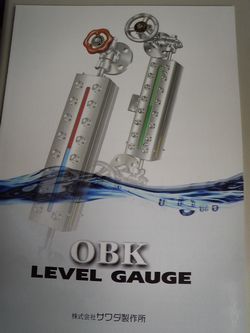
ガラス式液面計のことや弊社製品のことがよくわからなくても、このカタログをご覧頂くだけで製品や部品をご発注できるよう、中味に工夫を凝らしています。
また背表紙もこの薄さで、一目で取り出せるようにしています。

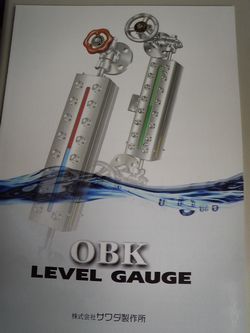
ガラス式液面計のことや弊社製品のことがよくわからなくても、このカタログをご覧頂くだけで製品や部品をご発注できるよう、中味に工夫を凝らしています。
また背表紙もこの薄さで、一目で取り出せるようにしています。

2007年03月29日(木)更新
弊社の取材記事が本になりました
今年初めに夕刊フジで取上げていただいた弊社の記事が本になりました。
神内 治 氏著 「勁く! 大化け前の関西元気企業」(現代創造社)
氏は表題を、しなやかなつよさ、しぶとく、へこたれないつよさの意味を込めて、「強く」ではなく、敢えて「勁く」にされたそうだ。
氏の関西企業への応援歌として、弊社もそうありたいと思う。
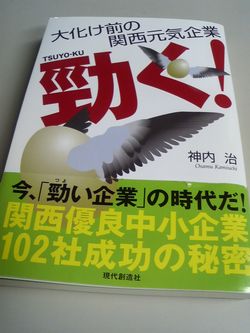
神内 治 氏著 「勁く! 大化け前の関西元気企業」(現代創造社)
氏は表題を、しなやかなつよさ、しぶとく、へこたれないつよさの意味を込めて、「強く」ではなく、敢えて「勁く」にされたそうだ。
氏の関西企業への応援歌として、弊社もそうありたいと思う。
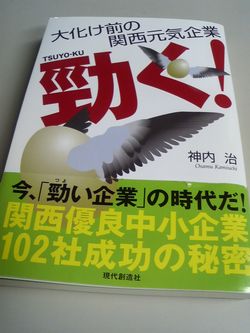
2007年03月28日(水)更新
社員教育で心がけていること
<質問>
社員教育で一番心がけていることは何ですか?
(東洋大学経営学部3年 渡辺麻貴さん)
弊社はISO9001取得企業ですので、社員の教育訓練についても毎年教育訓練計画を一人一人定めて行っています。
社員教育で一番心がけていることは、弊社の場合、いくつかのパターンに分かれます。
1.OJT
弊社も他の製造業と同じく、定年を迎える社員の技術伝承をどのように行うかが大きな課題です。
若手に対してはスキルマップを定め、半年毎に目標を設定し、OJTでベテランに指導してもらう、というやり方を取っています。
ベテランの方には既に定年を迎えている方もいらっしゃいますが、再雇用制度を利用して在職していただき、後進の指導に当たってもらっています。
スキルについての目標を達成すれば、きちんと評価に結びつける、ということを心がけています。
2.外部機関の利用
会社に新しい仕組みや知識が必要なときは外部からの手助けを得て、実際に導入してみる、試してみる、という方法を取っています。
例えば弊社の経営理念の中に「営業、製造、技術が三位一体となって」、とありますが、社内でのコミュニケーションをどう活発化するか、という課題があります。
そこで日常各部署で行う打合せや会議のやり方を見直し、相互学習型の会議の方法を導入しています。
これはファシリテーターや書記を定めてお互いが意見を十分出し合い、会議の結果について納得する、という会議手法です。
弊社は今年に入ってから管理職を対象に外部機関に研修をお願いし、この方法を取り入れています。
もちろん座学で学ぶだけでは導入できませんから、実際に会議の場で使っていただき、その振り返りを行う予定です。
また管理職に対しては、必要に応じて私自身がアドバイスすることを心がけています。
3.その他自己啓発
弊社の仕組みの中に、社員さんが関係する業務について自分から講習会やセミナーを受けて学びたいという場合に、会社として費用を負担するという制度を設けています。
この場合は自分で学んだことのレポートを出してもらったり、所属部署にフィードバックしてもらうという程度ですが、この制度を利用して大阪府工業協会の夜学に行かれ、優秀な成績で協会から表彰を受けた社員さんもいます。
社員教育で一番心がけていることは何ですか?
(東洋大学経営学部3年 渡辺麻貴さん)
弊社はISO9001取得企業ですので、社員の教育訓練についても毎年教育訓練計画を一人一人定めて行っています。
社員教育で一番心がけていることは、弊社の場合、いくつかのパターンに分かれます。
1.OJT
弊社も他の製造業と同じく、定年を迎える社員の技術伝承をどのように行うかが大きな課題です。
若手に対してはスキルマップを定め、半年毎に目標を設定し、OJTでベテランに指導してもらう、というやり方を取っています。
ベテランの方には既に定年を迎えている方もいらっしゃいますが、再雇用制度を利用して在職していただき、後進の指導に当たってもらっています。
スキルについての目標を達成すれば、きちんと評価に結びつける、ということを心がけています。
2.外部機関の利用
会社に新しい仕組みや知識が必要なときは外部からの手助けを得て、実際に導入してみる、試してみる、という方法を取っています。
例えば弊社の経営理念の中に「営業、製造、技術が三位一体となって」、とありますが、社内でのコミュニケーションをどう活発化するか、という課題があります。
そこで日常各部署で行う打合せや会議のやり方を見直し、相互学習型の会議の方法を導入しています。
これはファシリテーターや書記を定めてお互いが意見を十分出し合い、会議の結果について納得する、という会議手法です。
弊社は今年に入ってから管理職を対象に外部機関に研修をお願いし、この方法を取り入れています。
もちろん座学で学ぶだけでは導入できませんから、実際に会議の場で使っていただき、その振り返りを行う予定です。
また管理職に対しては、必要に応じて私自身がアドバイスすることを心がけています。
3.その他自己啓発
弊社の仕組みの中に、社員さんが関係する業務について自分から講習会やセミナーを受けて学びたいという場合に、会社として費用を負担するという制度を設けています。
この場合は自分で学んだことのレポートを出してもらったり、所属部署にフィードバックしてもらうという程度ですが、この制度を利用して大阪府工業協会の夜学に行かれ、優秀な成績で協会から表彰を受けた社員さんもいます。
2007年03月26日(月)更新
販売管理システムを新たに導入しました
新しい販売管理システムを本日導入しました。
従来は、
①各営業部員が受注伝票を手書きで起票 -> ②営業事務員が受注伝票を見ながら販売管理システムへ入力 -> ③売上げ処理、
という手順でしたが、
これからは各営業部員が販売管理システムにデータを直接入力できるようになり、事務処理の軽減、また手書き伝票の廃止ができます。
サワダ製作所はお客さまからのお問い合わせから、受注、製造、出荷までのリードタイム短縮に日々努力しています。

従来は、
①各営業部員が受注伝票を手書きで起票 -> ②営業事務員が受注伝票を見ながら販売管理システムへ入力 -> ③売上げ処理、
という手順でしたが、
これからは各営業部員が販売管理システムにデータを直接入力できるようになり、事務処理の軽減、また手書き伝票の廃止ができます。
サワダ製作所はお客さまからのお問い合わせから、受注、製造、出荷までのリードタイム短縮に日々努力しています。

2007年03月23日(金)更新
社長を支えるために必要なこと
<質問>
自分が、もし現在の会社で一社員の立場だったとしたら、社長を支えるためにどんなことが必要で、どんなことが出来ると考えますか?
※社長ご自身がどんなフォローを望んでいらっしゃるかをお聞きしたく思います
(東洋大学経営学部3年 渡辺麻貴さん)
社長を支えるためには、
・あるべき姿を描き、考えることができる、
・社内、社外さまざまな人から意見を聴いて、まとめ、かつ伝えることができる、
・また社内、社外のさまざまな関係者を説得することができる、
・計画を立て、立てた計画をマネジメントできる、
・社長と意見が異なっても、社長が何故そのように考えているのかを汲み取った上で、意見を述べることができる、
といったことが必要だと思います。
特に最後については、そこをわかった上で意見を言うのと、わからないで意見を言うのでは大きな違いがあります。
また上記のことをするには大きなエネルギーが要ります。
そういったエネルギーを社員が持っているからこそ、社員は社長から最大の信頼が得られるのだと思います。
自分が、もし現在の会社で一社員の立場だったとしたら、社長を支えるためにどんなことが必要で、どんなことが出来ると考えますか?
※社長ご自身がどんなフォローを望んでいらっしゃるかをお聞きしたく思います
(東洋大学経営学部3年 渡辺麻貴さん)
社長を支えるためには、
・あるべき姿を描き、考えることができる、
・社内、社外さまざまな人から意見を聴いて、まとめ、かつ伝えることができる、
・また社内、社外のさまざまな関係者を説得することができる、
・計画を立て、立てた計画をマネジメントできる、
・社長と意見が異なっても、社長が何故そのように考えているのかを汲み取った上で、意見を述べることができる、
といったことが必要だと思います。
特に最後については、そこをわかった上で意見を言うのと、わからないで意見を言うのでは大きな違いがあります。
また上記のことをするには大きなエネルギーが要ります。
そういったエネルギーを社員が持っているからこそ、社員は社長から最大の信頼が得られるのだと思います。
2007年03月20日(火)更新
中国の水面計
中国の水面計の写真を見る機会を得ました。
炉筒煙管ボイラーという、日本でも工場やビルなどに使用されているボイラー用の水面計です。
通常、日本では「反射式」というガラス溝の屈折で水位が確認できる水面計を用いますが、中国では「透視式」という水面計が用いられていました。
これは水面計の後部からライトを当てて水位を確認する方式です。

あと「二色式」というプリズムの現象を利用した水面計も使われているようです。

透視式も二色式も日本の炉筒煙管ボイラーでは使われている例を正直知りません。
たぶん水面計の位置が高いところにあり、見やすくするようにしているのでしょう。
また二色式水面計は形としても国内では見られないユニークな形をしているようです。
国によって使われる水面計も違うものだと感じています。
炉筒煙管ボイラーという、日本でも工場やビルなどに使用されているボイラー用の水面計です。
通常、日本では「反射式」というガラス溝の屈折で水位が確認できる水面計を用いますが、中国では「透視式」という水面計が用いられていました。
これは水面計の後部からライトを当てて水位を確認する方式です。

あと「二色式」というプリズムの現象を利用した水面計も使われているようです。

透視式も二色式も日本の炉筒煙管ボイラーでは使われている例を正直知りません。
たぶん水面計の位置が高いところにあり、見やすくするようにしているのでしょう。
また二色式水面計は形としても国内では見られないユニークな形をしているようです。
国によって使われる水面計も違うものだと感じています。
2007年03月17日(土)更新
クリエイション・コア東大阪にて
クリエイション・コア東大阪は、中小の製造業が集積している東大阪市に設置されたものづくりに関する総合的な支援施設です。
製品や技術の常設展示室も設けられており、弊社も新製品ライトグラフの初号機を展示しています。
また施設ではコーディネーターの方々が日々ものづくりに関する様々な相談に乗っています。
昨日はコーディネーターの方々を対象に、弊社のこれまでの取り組みについてお話させていただきました。
1時間という限られた時間でしたが、弊社におけるWebでの取り組みとその成果について、またコンサルタントや公的支援機関を利用したマネジメントの仕方について述べさせていただきました。
製品や技術の常設展示室も設けられており、弊社も新製品ライトグラフの初号機を展示しています。
また施設ではコーディネーターの方々が日々ものづくりに関する様々な相談に乗っています。
昨日はコーディネーターの方々を対象に、弊社のこれまでの取り組みについてお話させていただきました。
1時間という限られた時間でしたが、弊社におけるWebでの取り組みとその成果について、またコンサルタントや公的支援機関を利用したマネジメントの仕方について述べさせていただきました。
| «前へ | 次へ» |
- 義経号の水面計を手掛けることになりました [05/13]
- マインドマップ 組織内インストラクターの資格を取りました [04/30]
- 盛和塾で稲盛経営者賞を受賞致しました [07/19]
- 岩手大学附属中学校様 工場見学その後 [07/16]
- 岩手大学教育学部附属中学校様 工場見学 [07/03]
- 半年間の取り組み [07/02]
- 本年もよろしくお願い申し上げます [01/07]
- エフラットのクラウド [11/26]
- 書籍「社長! 「非常識社員」はこう扱いなさい」を読みました [10/30]
- 第二回 3Sサミットに行ってきました [10/22]
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(1)
- 2013年7月(4)
- 2013年1月(1)
- 2012年11月(1)
- 2012年10月(4)
- 2012年9月(1)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(3)
- 2012年6月(6)
- 2012年5月(9)
- 2012年1月(2)
- 2011年9月(1)
- 2011年7月(2)
- 2011年6月(2)
- 2011年5月(1)
- 2011年4月(1)
- 2011年3月(2)
- 2011年2月(3)
- 2011年1月(3)
- 2010年12月(3)
- 2010年11月(2)
- 2010年10月(4)
- 2010年9月(5)
- 2010年8月(8)
- 2010年6月(1)
- 2010年5月(3)
- 2010年4月(8)
- 2010年2月(2)
- 2010年1月(2)
- 2009年12月(2)
- 2009年11月(5)
- 2009年10月(2)
- 2009年9月(8)
- 2009年8月(3)
- 2009年7月(5)
- 2009年6月(4)
- 2009年5月(8)
- 2009年4月(7)
- 2009年3月(6)
- 2009年2月(3)
- 2009年1月(3)
- 2008年12月(4)
- 2008年11月(3)
- 2008年10月(4)
- 2008年9月(5)
- 2008年8月(4)
- 2008年7月(9)
- 2008年6月(3)
- 2008年5月(4)
- 2008年4月(6)
- 2008年3月(9)
- 2008年2月(4)
- 2008年1月(8)
- 2007年12月(9)
- 2007年11月(15)
- 2007年10月(11)
- 2007年9月(11)
- 2007年8月(19)
- 2007年7月(10)
- 2007年6月(11)
- 2007年5月(9)
- 2007年4月(11)
- 2007年3月(13)
- 2007年2月(9)
- 2007年1月(14)
- 2006年12月(14)
- 2006年11月(12)
- 2006年10月(14)
- 2006年9月(12)
- 2006年8月(15)
- 2006年7月(13)
- 2006年6月(17)
- 2006年5月(19)
- 2006年4月(12)
- 2006年3月(1)
最新トラックバック
-
新刊『社長!「非常識社員」はこう扱いなさい!』店頭展開開始!
from なにわの社労士発~「今日もこんなええことありました」
新刊『社長!「非常識社員」はこう扱いなさい』の店頭展開が開始になりました。 昨日、FBで東京の神田啓文堂さんでの購入情報を得たのですが 大阪は今日からだと思ったので、朝一番で事務所の最寄りの書店である 紀伊国屋書店本町店さんにお邪魔したところ、まさに品出しの真っ最中でした! 書店員さんに「私の本なんです!どうぞよろしくお願いします!」とご挨拶。 そして新刊はこのよ -
読書について
from 学生が朝会や社会人セミナーに参加してみた感想を綴るブログ
いつもお世話になっている 経営者会報ブログ。 >>トップページ 経営者や国家資格保有者、個人事業主など 限... -
周りの雰囲気をよくする言葉
from アイデアホイホイ
いい雰囲気をつくる魔法の言葉 -
橋下府知事のシンポジューム映像
from 若手製造業 特殊変圧器メーカー 治部電機株式会社 代表取締役 治部 健 (じぶけん)日記
先日、澤田社長のブログで紹介された㈱共伸技研社長の加藤さんが大阪府知事橋下徹氏にはじめて会ったシンポジューム映像が公開されました! その1 その2 大阪リーガ... -
橋下知事に感謝の気持ちをお伝えしました!
from かっちゃん社長のブログ@工業用ブラシの共伸技研っ!
昨日のなぞの日記の答えですが(^^昨日の夜、橋下知事のパーティーに出席することができました。橋下知事に工場見学に来ていただきたい!と2月26日のブログでエントリーしたあと、お会いする人お会いする人に、話をしているうちに、パーティーの券をいただけるというお....
 ログイン
ログイン




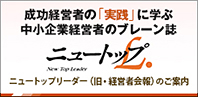




コメント一覧